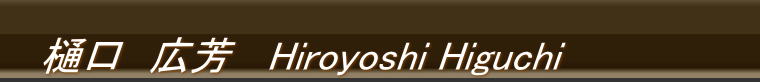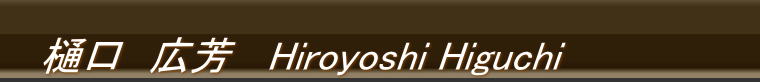主な受賞暦
★2023年6月 日本動物学会2023年度 Zoological Science Award および藤井良三賞 (土方直哉ほか6名と合同受賞)。対象論文は以下。
Hijikata, N., Yamaguchi, N. M., Hiraoka, E., Nakayama, F., Uchida, K.,
Tokita, K. and Higuchi, H. 2022. Satellite tracking of migration routes of the eastern buzzard (Buteo japonicus) in Japan through Sakhalin. Zoological Science 39:176-185.
★2017年6月 日本動物学会Zoological Science Award および藤井良三賞 (Chen Wenboほか8名と合同受賞).対象論文は以下。
Chen, W, Doko, T., Fujita, G., Hijikata, N., Tokita, K., Uchida, K., Konishi,
K., Hiraoka, E. and Higuchi, H. 2016. Migration of Tundra Swans (Cygnus columbianus) wintering in Japan using satellite tracking: identification of the Eastern Palearctic flyway. Zoological Science 33:63-72.
★2015年5月 野生生物保護功労者「環境大臣賞」
★2009年6月 日本動物学会Zoological Science Award および藤井良三賞 (山口典之ほか13名と合同受賞).対象論文は以下。
Yamaguchi, N., Hiraoka, E., Fujita, M., Hijikata, N., Ueta, M., Takagi,
K., Konno, S., Okuyama, M., Watanabe, Y., Osa, Y., Morishita, E., Tokita,
K., Umada, K., Fujita, G. and Higuchi, H. 2008. Spring migration routes of mallards Anas platyrhynchos that winter in Japan, determined from satellite telemetry. Zoological Science 25:875-881.
★2006年3月 日本生態学会「論文賞」(島崎彦人ほか5名と合同受賞).対象論文は以下。
Shimazaki, H., Tamura, M., Darman, Y., Andronov, V., Parilov, M., Nagendran,
M. and Higuchi, H. 2004. Network analysis of potential migration routes applied to identification
of important stopover sites for Oriental White Storks (Ciconia boyciana). Ecological Research 19:683-698.
★2006年3月 東京都三宅村「感謝状」(東京大学大学院農学生命科学研究科あて)
★1998年7月 (財)山階鳥類研究所「山階芳麿賞」
★1991年6月 (財)国立公園協会「田村賞」
★1977年7月 日本鳥学会「鳥学研究賞」
|