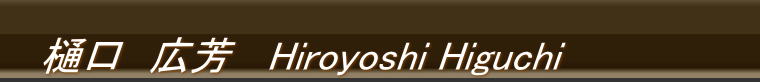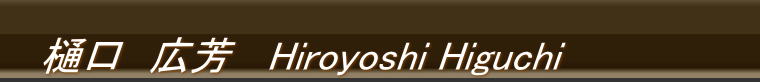|
2025年3月13日(木) 映画「花まんま」を試写会で鑑賞
大阪の下町を舞台に、両親を失った兄と妹が苦労しながら成長していく映画「花まんま」(朱川湊人さんの直木賞同名小説が原作)。そして妹の結婚相手となるのが、大学の助教でカラスの研究者。カラスとのいろいろな「交流」が、いくつか重要な部分で展開される。
https://hanamanma.com/news/info241009.html
私はこの映画の中で、カラスが水道の栓を回して水を飲む映像を提供している。例の横浜の水飲みガラス、グミの映像だ。コンピュータ画面の中で映し出されており、それをカラス研究者、太郎役の鈴鹿央士さんがかじりついて見ている。そんな経緯があって、試写会に招待されることになった次第。劇場版パンフレット(たぶん有料)の中でも、カラスの魅力や能力について写真付きで紹介している。
カラス関係者には興味深い内容となっている。また、カラス関連を抜きにしても、物語として珠玉の作品だ。涙なしには観ていられない。
一般公開は来月4月25日から。
|